自然法の法益保護について
- 2025.04.11
- 未分類
前回の引き続きだが、宿題にした「自然法」について簡単に述べておきたい。
1 「自然法」を定義しようとしても、どうも種々の要素及び表現があるようだ。以下、その特徴を文字化してみる。
①成文法として外形的に文字によって文章化された法文はない。少なくとも日本語の文章としては見ていない(私の勉強不足?)しかし、自然法概念のエッセンス(特質)は次のような言語表現が可能だろう。
②「社会的存在」の人間にとって、誰しも大多数の人が納得しうる原則的な共通の価値を宣言した共通の規律である。例えば、「殺すなかれ」、「盗むなかれ」、「犯すなかれ」等。但し、いずれの禁忌にも解除免責事項としての「正当防衛」とか「緊急避難」(?)的な(濃淡の差はあれど)一定の例外事項も含意されていると言ってよいであろう。要するに人倫の基本といってもよいのかも知れない。
③ もっとも「人倫」という表現は正しくない。(より明確かつ一般的に表現するなら)「人権」やその制度的担い手であるはずの「国権」の基本というべきか。即ち、「倫理」とか「道徳」という概念は、人種や民族、地域(あるいは国家)によって異なる価値規範であるから「自然法概念」にこれを混入・混同させてしまうと、自然法の基本的な性質に反するということになる。
④「国権」という概念も更に多義的曖昧な要素を持ち込みそうなので、自然法の対象法益に含めるには一層慎重でなければならない。
近時のウクライナやビルマ、チベット等の例を考えると、被害を受けていると目される国家(ないし前政権下の政府ないし国家や一般国民)に思いを致すと、限定された(条件付の)範囲内で、「国権」の保護も異質ではあるが一定の条件の下、自然法によって保護されるべき価値として容認されてもよいのかも知れない(その意味では中国に対するチベットや台湾の場合も同様であろう)。
2 そこで、「国権」も自然法の保護法益(自然法という規範によって保護されるべき利益)である、と法益の対象を拡大してもよいとされる場合の一定の条件とは何か。
① まず現政権によって駆逐打倒された前政権が一定の合理的あるいは「民主的」な国家制度によって運営(用)されていた政府であって
② 少なくとも前政権下の国民の大多数がその政府を支持ないし好意をもって統治されていたこと
③ のみならず、現政権下の大多数の国民もまた前政権に対し、より好感をもっており
④ 大多数の国民が現政権に対し、前政権より多くの反感を招いていること
⑤ 現政権が制度的に反対勢力によって交替可能な政治制度(いわゆる合理性のある選挙ないし類似の代表制度)を有すること
3 なお更に付言すれば、私自身は、一般論として現行の日本の選挙制度に対して多くの疑問をもっている。その大きな理由の一つは、「棄権」の権利が制度的に保障されていないことにある。選挙制度を合理的に検討する限り、棄権率が50%を越えた場合の「選挙」というのは、本当に民意を反映していると主張できるのだろうか。否であろう。
そこで、私は前項②~④において、敢えて「国民の大多数」とか「大多数の国民」という用語を用いた。単純な「相対的多数」を「民意」と表現するのは誤りである。
「棄権」という行為を選択した国民は、当該選挙のどの候補者も意に沿わない、と判断しているからなのかも知れない。
忙しいからとか、面倒だから選挙に行かなかったという人ばかりではない。殊に、たまたま表面化した最近の金権政治騒動などを見ていると、もういいかげんにしろと言って、意識(意図)的に棄権する人が増えていると断じても過言ではなかろう。
結論的に言えば、棄権票を無視ないし軽視(しようと) するのは現行選挙制度の重大な欠陥なのである。私論ではあるが、本当は棄権率が50%を超えたら、選挙はやり直すべきなのであろう。
さりとして、選挙に金がかかるのは、政治家(候補者)ばかりではない。選挙を運営実施する国や都道府県や地方自治体もまた多額の経費を出費しており、その原資は税金である。頭の痛い問題であるが、ここは原則(理)主義を貫徹したい。
4 ただここでは「自然法」がテーマなので、話を戻そう。国家や自治体もまた自然法による保護法益の対象である。とはいっても、国家や自治体の意思決定者も大多数の国民や住民によって民主的に選任された存在でなければならない。
その意味では、現状では棄権する完全な権利を「軽視」ないし「無視」するような現行の選挙制度を前提にする限り、「国益」や「国権」は自然法の保護法益の対象とはならない、というべきである。
自然法の内容については、やはり前記1の②程度の内容にとどめる以上の検討は未了である。おいおい勉強していくしかないが、なんとも頼りない結果である。
5 「大多数」の支持か否かは、一応定量的に評価可能な判断と言えるであろうが、その支持の対象目的となると、余程質問なりアンケート調査なりを慎重に検討する外なく、多分、複数(という以上に相当数)の関係者による協議と意見交換とが前提となろう。
要するに、「民主主義」なる原理あるいは政治手法は誠に面倒かつ非効率的な方法(制度)であって、実務的には不適とさえ言われかねない不完全な政治制度なのである。
さりとて、人間は歴史的には「民主主義」に代るべき一定程度公平で優れた実用的政治制度を手にしていない。
一度ロシアにおける一般民衆の付和雷同性に触れたが、この悪癖はロシアに限らないし、中国だろうがアメリカだろうが、そして日本であろうが、色合いの違いはあっても本質的には皆同じと言ってよい。結局その改革は正しい(まともな)教育の実行しかないのであろう。しかし、「百年河清を待つ(黄河のことで不可能の意)」では困る。
恐らくこれを避けるなら、教育あるいは正確な情報知識の速やかな普及しかなかろう。
しかしながら、SNSだとか携帯電話だとかは、このままでは危険な道具でしかなくなるであろう。
-
前の記事
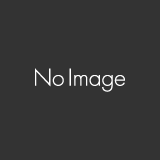
先端科学(担手としての国家)との対峙 2025.02.14
-
次の記事
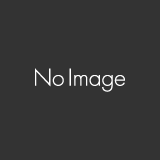
当面の21世紀展望 2025.05.14